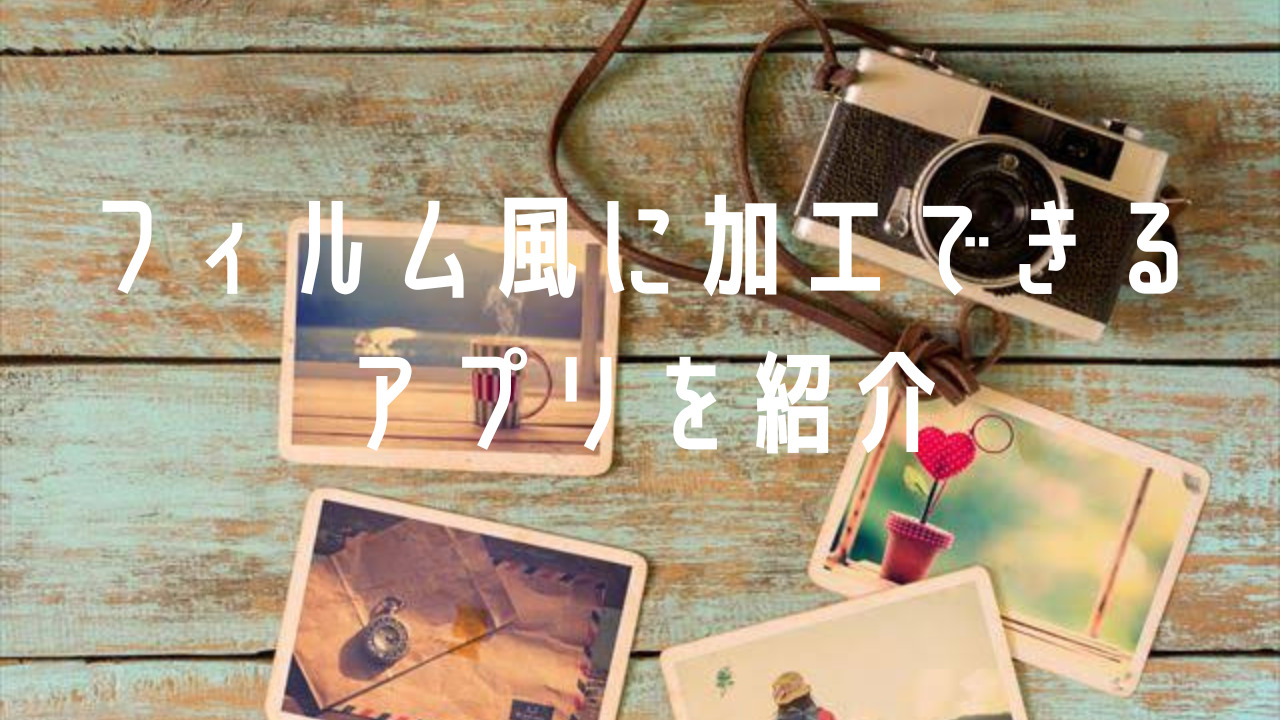フィルムカメラを始める前に知っておくべきこと
フィルムカメラとは?デジタルカメラとの違い

フィルムカメラは、光をフィルムに焼き付けて写真を撮るカメラのことです。現在主流となっているデジタルカメラ(ミラーレス・一眼レフ・スマホのカメラなど)は、撮影データをデジタル形式で保存するのに対し、フィルムカメラは物理的なフィルムに記録されます。
違いを以下の表にまとめまてみました。
| 比較項目 | フィルムカメラ | デジタルカメラ |
|---|---|---|
| 保存方法 | フィルムに化学的に記録 | メモリーカードにデータ保存 |
| 撮影枚数 | 1本で24〜36枚(ハーフサイズなら72枚) | 容量次第で何百〜何千枚 |
| 現像が必要か | 必須(フィルムを現像しないと見られない) | その場で確認可能 |
| 色味や質感 | 独特な発色・コントラスト・粒状感 | 設定次第で自由に調整可能 |
| 撮影の難易度 | 露出・ピント調整が必要 | 自動設定で簡単に撮影可能 |

しかし、その手間こそが、フィルムカメラならではの楽しさでもあります!
フィルムカメラの魅力と楽しみ方

フィルムカメラが一部の人に人気なのは、デジタルカメラにはない魅力がたくさんあるからです。
フィルムカメラの楽しみ方について考えてみました。
デジタルにはない「味わいのある写真」が撮れる
フィルムカメラの最大の魅力は、独特の質感や色味です。デジタルカメラでは後から加工することで似た雰囲気を作れますが、本物のフィルム写真が持つ質感や深みは、フィルム特有のもの。
フィルムの種類によって色味やコントラストも変わるため、自分好みのフィルムを探す楽しみもあります。
一枚一枚を大切に撮影するようになる
デジタルカメラでは、気軽にシャッターを切り、失敗したらすぐに消すことができます。
しかし、フィルムカメラは1本あたりの撮影枚数が限られているため、慎重に構図や光の入り方を考えて撮影するようになります。
これにより、写真のクオリティが上がり、撮影スキルの向上にもつながります。
現像するまで仕上がりが分からないドキドキ感
フィルムカメラでは、撮影した写真をすぐに確認することができません。現像が終わるまで仕上がりが分からないため、「どんな写真になっているのか」というワクワク感を楽しめます。
この“待つ楽しみ”が、フィルムカメラならではの醍醐味です。
レトロなデザインでファッションアイテムにもなる
フィルムカメラは、デジタルカメラと比べてデザイン性の高いものが多く、持ち歩くだけでおしゃれな雰囲気を演出できます。
特にコンパクトフィルムカメラは手軽に持ち歩けるので、カメラをファッションの一部として楽しむ人も増えています。
スマホやデジタルカメラとは違った撮影体験ができる
フィルムカメラは、オートフォーカスやオート露出の機能がないものも多く、すべての設定を手動で行う必要があります。
そのため、撮影そのものに集中でき、写真を撮ること自体が楽しくなります。
フィルムカメラの始め方の流れ

フィルムカメラを始めるにあたって、基本的な流れを理解しておくことが重要です。大まかな流れは以下の5ステップになります。
自分に合ったフィルムカメラを選ぶ
↓
撮影するためのフィルムを選ぶ
↓
カメラの使い方を覚える
↓
撮影したフィルムを現像する
↓
写真をデータ化またはプリントして楽しむ
それでは、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
初心者向けフィルムカメラの選び方
フィルムカメラと一口に言っても、多くの種類があります。初心者向けの選び方として、以下のポイントを押さえておきましょう。
フィルムカメラの種類を知る
フィルムカメラには、大きく分けて以下の4種類があります。
フィルムカメラの種類
- 使い捨てフィルムカメラ(初心者向け)
→ 操作が簡単で、軽量。オートフォーカス機能や内蔵フラッシュが付いているものも多い。
- コンパクトフィルムカメラ(初心者向け)
→ 操作が簡単で、軽量。オートフォーカス機能や内蔵フラッシュが付いているものも多い。
- 一眼レフフィルムカメラ(中級者向け)
→ レンズ交換が可能で、本格的な撮影が楽しめる。
- レンジファインダーカメラ(上級者向け)
→ ピント合わせが独特で難しいが、シャッター音が静かでコンパクト。
新品 or 中古の選択
フィルムカメラは生産終了しているモデルが多く、現在流通しているものの多くは中古品です。初心者は、比較的安価で手に入る中古カメラがおすすめ。ただし、購入時は「動作確認済み」や「整備済み」のものを選びましょう。
この記事では、中古フィルムカメラを買う際の注意点や選ぶポイントについて解説した記事も是非ご覧ください。
初心者におすすめのカメラ
初心者におすすめのカメラとして、以下のモデルがあります。
- コンパクトカメラ:KODAK ULTRA F9、Kodak EKTAR H35
- 一眼レフカメラ:Nikon FE、PENTAX SP、CONTAX Aria
上記のモデルについて紹介した記事も是非ご覧ください。

まずは操作が簡単なコンパクトカメラからスタートし、慣れてきたら一眼レフにステップアップするのがおすすめです。
どのフィルムを選べばいい?種類と特徴を解説

フィルムカメラには、さまざまな種類のフィルムがあります。撮影するシーンや好みによって選びましょう。
カラーネガフィルム(初心者向け)
- 一般的に最も流通しているフィルムで、街の写真屋さんでも現像可能。
- 色味がナチュラルで扱いやすい。
- 代表的なフィルム:Kodak Gold 200、FUJIFILM 400
モノクロフィルム(白黒フィルム)(中級者向け)
- クラシックな雰囲気の写真が撮れる。
- 一般的な現像所では処理できないことがある。
- 代表的なフィルム:Kodak Tri-X 400、Ilford FP4+
スライドフィルム(ポジフィルム)(上級者向け)
- 発色が鮮やかでコントラストが強い。
- 露出設定がシビアで、初心者にはやや難しい。
- 代表的なフィルム:FUJIFILM Velvia 50、Kodak E100

それぞれのフィルムの写りの違いは、「フィルム作例一覧ページ」がありますので参考にしてみてください。
-

-
フィルムの選び方を紹介!フィルムの種類や特徴について【初めてフィルムカメラを使う方向け】
続きを見る
フィルム名に書かれている数字はなに?ISO感度について
フィルムのパッケージには、100 や 400 などの数値が記載されています。この数字は、フィルムがどの程度の光を必要とするかを表しており、次のような特徴があります。
| ISO感度 | 特徴 | 適した撮影シーン |
|---|---|---|
| ISO 100 | 低感度、光を多く必要とする | 晴れた屋外、明るい昼間 |
| ISO 200 | やや低感度 | 少し曇りの日、屋外撮影全般 |
| ISO 400 | 中感度、バランスが良い | 曇天、日陰、屋内(光量のある場所) |
| ISO 800 | 高感度、暗い場所でも撮影可能 | 屋内、夕方、夜景 |
| ISO 1600 | 超高感度、暗所でも撮影しやすい | 室内、夜間、ライブ会場 |
数値が小さいほど光が多く必要で、晴れた屋外での撮影に適しています。一方、数値が大きくなるほど暗い場所でも撮影できますが、粒状感(ノイズ)が増えやすくなります。
ISOが高いほうが、暗い場所でも撮影することができますが、逆にISO1600を屋外で使用すると写真が真っ白になることがあります。
私が撮影した写真でISO値と撮影場所がミスマッチした例を一部紹介します。一枚目は写真が真っ白になる(白トビ)、二枚目は、黒くなる(黒つぶれ)が発生。
(逆にミスマッチもいい味になるときもありますが、((´∀`))ケラケラ)

ISO400のモノクロフィルムで逆光撮影した写真

ISO200のネガフィルムで夕暮れ時を撮影した写真

フィルムカメラの使い方【基本操作をマスターしよう】
フィルムカメラの基本操作は、以下の流れで行います。
-
フィルムをカメラにセットする
→ フィルムのリーダー部分をスプールに差し込み、正しく巻き取る。 -
ISO(感度)を設定する
→ フィルムに記載されたISO(例:100、200、400など)をカメラのダイヤルで設定。 -
ピントを合わせる
→ マニュアルフォーカスの場合、ファインダーを覗きながらピントリングを回して調整。 -
露出を調整する
→ シャッタースピードと絞り(F値)を適切に設定する。 -
シャッターを切る
→ フィルムを無駄にしないよう、しっかりと構図を決めてから撮影。 -
フィルムを巻き戻す(最重要)
→ 撮影が終わったら、フィルムを巻き戻して取り出す。

ここに関しては、文章での説明より動画の方がわかりやすいと思うので参考に載せておきますね!

最重要
カメラの裏蓋を開ける前に必ずフィルムを巻き取ろう!
楽しくフィルム撮影を終えたら、カメラの裏蓋を開ける前に、必ずフィルムを巻き取ることを忘れないでください!
フィルムを巻き取るとは、撮影後にフィルムを元のパトローネ(筒状のケース)へ戻すことを指します。
これをしないまま裏蓋を開けてしまうと、フィルムが光にさらされ、すべて感光して写真が真っ白になってしまいます。
オート機なら自動で巻き取ってくれますが、よくあるコンパクトカメラ(KODAK ULTRA F9、Kodak EKTAR H35)はぐるぐると自分で巻き取らないといけません。


フィルム現像の流れ【自家現像と専門店の違い】
撮影したフィルムは、現像しないと写真として見ることができません。現像には「専門店に依頼する方法」と「自家現像する方法」の2つがあります。
専門店に依頼する(初心者向け)
- カメラ店や現像専門店にフィルムを持ち込んで現像してもらう方法。
- 料金は現像のみで800~1500円程度。
- 仕上がりに数日かかる場合があるが、確実に綺麗に現像できる。
関連記事
自家現像(上級者向け)

- 自分で薬品を使ってフィルムを現像する方法。
- 初期費用はかかるが、長期的にはコストを抑えられる。
- 失敗するリスクがあるため、ある程度の知識と経験が必要。

スマホやPCで楽しむためのデータ化・プリント方法

お店などで現像してもらったネガのままだと何の写真だかわかりませんよね。
撮影したフィルムをスマホやPCで楽しむには、データ化する必要があります。
スキャンしてデータ化する
- 現像時に「データ化サービス」を利用すると、スマホやPCに取り込めるデータを作ってもらえます。
- 専用のフィルムスキャナーを使えば、自宅でスキャンすることも可能。
プリントしてアルバムにする
- データ化だけでなく、写真プリントしてアルバムを作るのもおすすめです。
- 写真店やオンラインサービスを利用すれば、高品質なプリントが可能。

フィルムカメラを続けるために知っておきたいこと

ここまでフィルムカメラの始め方としてカメラの選び方からデータ化まで紹介して、皆さんもフィルムカメラをやってみたいと思った方も多いのではないでしょうか。

フィルムカメラはデジタルと違い、手間やコストがかかります。そのため、長く楽しむためには以下のポイントを押さえておきましょう。
フィルムの入手方法
近年、フィルムの価格が上昇しているため、安定して入手できる販売店を知っておくことが大切です。
フィルムは1本単位で購入するより、まとめ買いをすることで1本あたりの価格を抑えられます。特に人気の「Kodak Gold」や「FUJIFILM 400」などはセット販売されることが多く、Amazonや楽天市場では3本セットや5本セットを購入するとお得です。
また、海外の通販サイト(B&H、Adorama)では日本よりも安く販売されていることがあるので、チェックしてみるのもおすすめです。
ポイント
- Amazonや楽天でまとめ買い
- カメラ専門店(ヨドバシカメラ・ビックカメラなど)
- 海外通販(B&H、Adoramaなど)で安く購入

コストを抑える工夫
フィルムカメラは撮影ごとにフィルム代や現像代がかかります。コストを抑える方法として、以下の工夫ができます。
ポイント
- ハーフサイズカメラを使う(Kodak EKTAR H35など)
⇒1本のフィルムで2倍多く撮影することができる。(36枚撮りであれば、72枚撮影可能。) - モノクロフィルムを使い、自家現像する
⇒モノクロフィルムはカラーネガに比べ安価であることが多く、自家現像すればコストカットできます。 - フィルムをまとめて現像して割引を活用する
⇒お店によりますが、まとめて現像すれば割引が効くことがあります。
保管・メンテナンス
フィルムカメラは精密機械のため、適切な保管とメンテナンスが必要です。
ポイント
- 湿気を防ぐため、防湿庫に保管
- 定期的にシャッターを切り、動作確認をする
- オーバーホールを依頼し、長く使えるようにする

フィルム代・現像代はいくら?ランニングコストを把握しよう
フィルムカメラを続ける上で、ランニングコストをしっかり把握しておくことも大切です。
使用するフィルムの種類や現像方法によってコストは変動しますが、年間10万円程度でフィルムカメラを楽しむことができます。
-

-
フィルムカメラを始めるにはどれくらいお金がかかるのか解説
続きを見る
フィルム代
- カラーネガフィルム:1本 1,500円~2,500円
- モノクロフィルム:1本 1,200円~2,500円
- スライドフィルム:1本 2,500円~4,000円
現像代
- カラー現像:800円~1,500円(1本)
- モノクロ現像:1,000円~2,000円(1本)
スキャン(データ化)代
- 基本スキャン:500円~1,500円
合計コストの目安
例えば、36枚撮りのフィルムを1本使用し、現像+スキャンすると 約3,000円~5,000円 ほどのコストがかかります。
フィルムカメラを始めるには、最低でも1~2万円のカメラ本体費用と月々のフィルム代+現像代(約5,000円~8,000円)が必要になります。年間で考えると、10万円前後の予算を見ておくと安心です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| カメラ本体(中古) | 15,000円 |
| フィルム(1本1,500円 × 24本) | 36,000円 |
| 現像・データ化(1本2,000円 × 24本) | 48,000円 |
| 合計 | 約99,000円 |

コストを抑えながらも、フィルムカメラの楽しさを最大限に引き出しましょう!
加工アプリやレタッチでデジタル写真をフィルム風に
ここまで記事を読んでやっぱりフィルムって大変そうと思った方もいたのでは?!
スマホアプリやレタッチでフィルム風に加工する方法も合わせて紹介しておきますね!

加工アプリでフィルム風を再現させる
スマホアプリを使えば、手軽にフィルム風の写真を作れます。以下のアプリは、無料または安価で利用できるためおすすめです。
| アプリ名 | 特徴 | ダウンロード(iPhone) | ダウンロード(Android) |
|---|---|---|---|
| HUJI Cam | 撮るだけで写ルンです風 | 📲 iPhone版 | 📲 Android版 |
| RNI Films | 本物のフィルムカラーを再現 | 📲 iPhone版 | ※現在Android版は提供されていません |
| FIMO | フィルムカメラの操作感あり | 📲 iPhone版 | 📲 Android版 |


RNI Filmsで加工した写真

HUJI Camで加工した写真

-

-
『写ルンです』で撮ったようなフィルムライクな写真に仕上がる無料アプリを3つ紹介
続きを見る
編集ソフト(Lightroom、Photoshop)でフィルム風に仕上げる
アプリだけでなく、PCの編集ソフト(Lightroom、Photoshop)を使えば、さらに本格的なフィルム風の仕上がりにできます。
「Lightroom フィルム風 プリセット」と検索すれば、デジタル写真をフィルム風に変身させることができるかも。

Lightroomで『FUJICOLOR PRO 400H』を再現してみた

おわりに

というわけで、今回は初心者向けに「フィルムカメラの始め方と魅力」というテーマでカメラ選び方から現像、データ化までのやり方やランニングコスト、フィルム風レタッチ方法など盛りだくさんで紹介しました。
なんだかんだ言って結構やることが多いなあと感じた方もいらっしゃると思います。それで始められないより、まずは安いものを買ってしまって写真を撮って楽しみながらやり方を少しずつ覚えていくのがいいのかなと思います!
いちばん簡単にフィルムカメラを始める方法は富士フイルムの『写ルンです』を買うことですね!
フィルムカメラの一歩を是非踏み出してみよう!